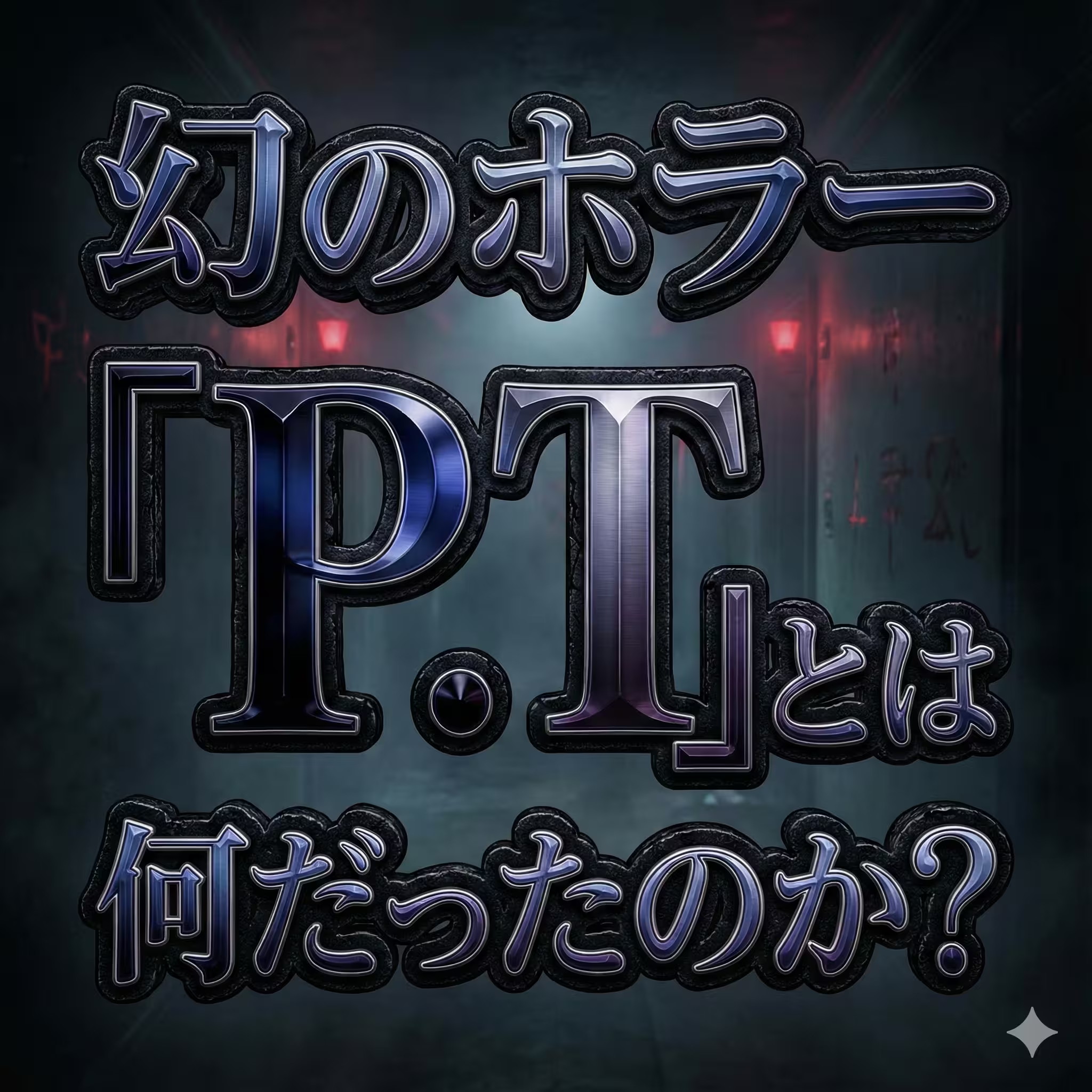ホラー映画やゲームの話題になると、必ずと言っていいほど「あの伝説のゲーム」の名前が挙がり、話についていけずに愛想笑いを浮かべてやり過ごしていませんか?
「怖すぎて配信停止になったらしいよ」
という噂レベルの話は知っているけれど、具体的に何が凄かったのか、なぜ10年以上経っても熱狂的に語られるのか、その本質までは知らないという方も多いでしょう。
ネットで検索しても、専門用語だらけの解説記事か、ただ「怖かった」と叫んでいるだけの感想文ばかりで、結局この現象の全体像が掴めずにモヤモヤしたままブラウザを閉じてしまう……
そんな経験はありませんか?
この記事では、2014年に突如現れ、そして消滅した幻のホラーゲーム『P.T.』について、その
技術的革新性から心理学的トリック、さらには企業とクリエイターの壮絶なドラマ
に至るまで、あらゆる角度から徹底的に解剖します。
業界の裏側を知り尽くした現役ウェブライターである私が、膨大な資料とデータ、そして独自の視点を交えて、この「現代の神話」を紐解いていきます。
この記事を読めば、あなたは『P.T.』という現象のすべてを理解し、単なる怪談話としてではなく、デジタル文化史における重要な事件としてこの作品を語れるようになります。
明日のランチタイムや飲み会の席で、
「実はね、あのゲームの正体って……」
と、誰かに話したくてたまらなくなるはずです。
結論から申し上げます。
『P.T.』とは、単なるホラーゲームの体験版ではありません。
それは、我々の脳の認知システムをハッキングし、デジタル社会の脆弱性を暴き出した、再現不可能な
「呪いの芸術品」
なのです。
満員電車の揺れに身を任せながら、ふと考えることがあります。
私が今、吊革を握りしめて耐えているこの「通勤」という終わりのないループと、あのL字型の廊下を延々と周回させられた体験。
精神的な摩耗という意味では、どちらがよりホラーなのだろうか、と。
ご挨拶が遅れました。
長崎の坂の町から上京して早20数年、現在は東京の片隅で夫の両親と同居しながら、育児と仕事と家事のトライアングルに揉まれている中年ウェブライターです。
普段はしがない会社員として、片道1時間の電車通勤をこなしています。
この1時間という時間は、人間観察と妄想に費やすには十分すぎる長さでして。
隣のおじさんのイヤホンから漏れる演歌のリズムに合わせながら、世の中の理不尽について思考を巡らせるのが日課となっています。
さて、時計の針を少し巻き戻しましょう。
あれは2014年の夏でした。
当時、息子はまだ幼稚園に上がる前で、私は育児と仕事の狭間で白目を剥いていた時期です。
世間では『アナと雪の女王』が流行り、「ありのままで」なんて歌が聞こえてきましたが、私の現実は「ありのまま」でいたら家の中が崩壊するようなギリギリの状態でした。
そんな時に現れたのが『P.T.』でした。
たった数十分の、しかも無料の体験版。
それが配信停止から10年以上経った今でも、まるで古傷のように疼くのはなぜなのか。
今日は主婦の目線と、ライターとしての執念深いリサーチ力を総動員して、この「現代の怪談」の正体を暴いてみたいと思います。
覚悟して、あの湿った廊下へ戻りましょう。
スポンサーリンク
映画「シークレット・マツシタ」はなぜつまらないのか?【感想レビュー】南米発・日系ホラーの「額に死」が招いた悲劇と爆笑を徹底解説
【元コナミ】小島秀夫監督という預言者が遺したミームの全貌!私たちは彼が視た未来の「その先」にいる【メタルギア】
2014年8月12日世界が騙された日

人間というのは、実に騙されやすい生き物です。
スーパーで「通常価格」の横に赤字で「半額」と書かれているだけで、大して欲しくもないお惣菜をカゴに入れてしまう。
これを行動経済学で
「アンカリング効果」
と言いますが、2014年のあの日、小島秀夫監督は世界規模でこの心理実験を行いました。
ドイツで開催されたGamescomのソニー・プレスカンファレンス。
そこで一本の映像が公開されました。
開発元としてクレジットされたのは
「7780s Studio」
誰も聞いたことのないインディーズスタジオです。
映像はフォトリアルですが、どこか粗削りで、不親切なUI(ユーザーインターフェース)。
これらはすべて、我々の期待値を「低く」設定するためのアンカー(錨)でした。
「無名の新人が作った実験作か。まあ無料だし、ちょっと触ってみるか」
という油断。
この油断があったからこそ、その後に襲い来る圧倒的なクオリティとのギャップ(コントラスト効果)が、脳髄を焼き切るほどの衝撃を生んだのです。
私も当時、夜中にこっそりダウンロードしました。
夫と義両親が寝静まったあと、リビングのテレビで。
まさかそれが、ゲーム史に残る巨大な「釣り」だとも知らずに。
「静岡」に隠されたダジャレのような真実
実はこの「7780s Studio」という名前、とんでもない伏線が張られていたんです。
鋭い考察班たちが即座に特定したのですが、「7780」という数字、これ静岡県の総面積(約7,780平方キロメートル)なんですよね。
そして「静岡(Shizuoka)」とは、日本のゲームコミュニティにおいて『サイレントヒル(Silent Hill)』を指す隠語として長年親しまれてきた言葉です。
「静=Silent」「岡=Hill」という直訳スラングですね。
末尾の「s」は、後に判明するタイトル『Silent Hills』という複数形を示唆している。
つまり、
「7780s Studio」とは「静岡(サイレントヒル)スタジオ」のダブルミーニング
だったのである。
このダジャレのような暗号に気づいたとき、私は思わず膝を打ちましたよ。
深夜のリビングで一人、
「やられた!」
と唸ってしまった。
インディーズを装うことで、プレイヤーから「分析的な視点」を奪い、無防備な背中を刺す。
これはホラーにおける最高のマナー違反であり、最高の演出だったのです。
この「7780s Studio」の正体が暴かれ、ゲームをクリアした先でノーマン・リーダスの顔と小島秀夫、ギレルモ・デル・トロの名前が出た瞬間、世界中のゲーマーが熱狂しました。
それは単なる新作発表ではなく、壮大なマジックショーのフィナーレを見せられたようなカタルシスでした。
スポンサーリンク
Fox Engineが描いた「空気の腐敗」

『P.T.』のグラフィックは、ただ綺麗なだけではありません。
なんというか、
「空気が腐っている」
感じがするのです。
私の家の洗面所も掃除をサボると似たような淀んだ空気になりますが、あのゲームの廊下には、生活感と死臭が同居していました。
使用されたのは、小島プロダクション自慢の「Fox Engine」。
本来は『メタルギアソリッドV』のような広大なオープンワールドを描くためのエンジンですが、それをたった一本の「廊下」を描くためだけに使用したのです。
このリソースの集中投下は、物理ベースレンダリング(PBR)という技術によって、異次元のリアリティを生み出しました。
壁紙の浮き、床に落ちた薬の錠剤、ゴキブリの甲殻のテカリ。
これらが妙にリアルであればあるほど、我々の脳は混乱します。
「これは現実だ」
と認識するシステムと、
「いや、何かがおかしい」
と警告するシステムが衝突する。
いわゆる「不気味の谷」現象です。
通常、不気味の谷はロボットやCGキャラクターに対して起こりますが、『P.T.』は空間そのものを不気味の谷に突き落としました。
照明の落ち方が、どこか生理的に不安を煽る。
見慣れたはずの「家」という安全地帯が、異界に侵食されていくプロセス。
これは、毎晩帰宅するたびに、義母の機嫌が良いか悪いかを探る時の緊張感に似ています……
いえ、冗談です。
でも、日常の中に潜む違和感こそが、怪獣が暴れるよりも怖いというのは真理ですよね。
聴覚へのダイレクトアタック
そして、音です。
ヘッドホンをしてプレイした時のあの感覚、覚えていますか?
右耳の後ろで女性のすすり泣きが聞こえ、振り返ると左前方から赤子の笑い声がする。
バイノーラル録音による3Dオーディオは、プレイヤーの空間認識能力を狂わせました。
さらに興味深いのが、低周波音(インフラサウンド)の使用疑惑です。
19Hz付近の音は、人間の耳には聞こえませんが、脳や身体は感知します。
不安感、寒気、吐き気、そして「幽霊の気配」を感じさせる音域として知られています。
イギリスの研究では、コンサート会場でこっそり低周波音を流したところ、多くの観客が
「わけもなく悲しくなった」
「寒気がした」
と報告したそうです。
『P.T.』のプレイ中に感じたあの胸のざわめきや生理的な不快感は、オカルトではなく、音響兵器のような科学的アプローチによるものだった可能性が高いのです。
静寂こそが、最大の暴力。
我が家の息子が静かな時は大抵ろくでもない悪戯をしている時ですが、それと同じ理屈です。
スポンサーリンク
ループ構造と学習性無力感

ゲームの構造はシンプルです。
L字型の廊下を歩き、突き当たりの扉を開け、また同じ廊下の入り口に戻る。
これを繰り返すだけ。
しかし、このループ構造こそが、心理学で言う
「学習性無力感」
を生み出す装置でした。
犬に
「何をしても電気ショックから逃げられない」
という状況を与え続けると、やがて逃げることすら諦めてうずくまるようになります。
『P.T.』のプレイヤーも同じです。
進んでも進んでも出口がない。
ループするたびに環境は悪化し、照明は赤くなり、冷蔵庫からは血が滴る。
「努力しても報われない」
という絶望感。
これは現代社会の縮図のようでもありますね。
満員電車で会社に行き、働いて帰り、また満員電車に乗る。
その繰り返しの中で、ふと
「私は何のために生きているのか?」
と虚無に襲われる瞬間。
『P.T.』は、その虚無をホラーとしてエンタメ化しました。
従来のホラーゲームが「新しい場所へ進む恐怖」を描いていたのに対し、『P.T.』は
「知っているはずの場所が変貌する恐怖」
を描いたのです。
最も安全であるはずの「家」が、最も危険な場所に変わる。
主婦としては、片付けても片付けても数分後には散らかっているリビングを見た時の絶望感に近いものを感じます。
あれも一種のホラーですからね。
スポンサーリンク
怨霊「リサ」の正体彼女はずっとそこにいた

ここからが、超俯瞰的な視点での考察の本番です。
このゲームの恐怖の象徴である幽霊「リサ」。
片目を失い、血まみれの服を着た彼女は、神出鬼没で、いつ現れるかわからないランダムな存在だと思われていました。
しかし、配信停止から数年後、Lance McDonald氏というハッカーがカメラを操作(ハッキング)して、とんでもない事実を暴きました。
リサは、ランダムに現れていたのではありません。
ゲーム開始直後から、ずっとプレイヤーの背後に固定(ペアレント)されていたのです。
想像してみてください。
あなたが廊下を歩いているとき、あなたが懐中電灯で壁を照らしているとき、あなたがふと立ち止まったとき。
画面には映らないけれど、カメラ(プレイヤーの視点)の数センチ後ろに、常に血まみれの女が張り付いていたのです。
プレイヤーが振り向くと、リサも合わせて背後に回り込むプログラムが組まれていました。
だからこそ、常に「気配」がしたのです。
影が変な方向に伸びたり、耳元で吐息が聞こえたりしたのは、演出上のフェイクや錯覚ではなく、実際にそこに「物体として」存在していたからです。
HADDへのハッキング
人間には
「HADD(過剰な行為主体検知)」
という本能があります。
草むらがガサッと揺れたとき、「風かな?」と思うより「ライオンだ!」と思った方が、生存率が高かったからです。
だから私たちは、何もないところに気配を感じやすい。
心霊現象の多くは、このHADDの誤作動だと言われています。
しかし『P.T.』は、この本能を逆手に取りました。
気配を感じるのは誤作動ではない。
本当にいるからだ。
通常のゲーム制作では、処理を軽くするために
「カメラに映っていないものは描画しない(カリング)」
というのが常識です。
しかし、小島チームはあえてその常識を破り、「見えないが存在する」状態を作り出しました。
これはもはや、デジタル空間に本物の幽霊を召喚したようなものです。
技術的なリソースの無駄遣い?
いえ、これこそが「第六感」をハックする究極のアルゴリズムです。
私も、義母の視線を感じて振り返ると誰もいない、ということがよくありますが、あれももしかしたらペアレント処理されているのかもしれませんね。
さらに、ハッキングによって判明した事実はこれだけではありません。
プレイヤーがバスルームに閉じ込められるシーン。
壁の向こうで足音が聞こえるだけですが、カメラを壁の外に出すと、リサは実際に廊下を独自の歩行アニメーションで歩き、ドアの前で立ち止まり、ドアノブに手をかける動作を行っていたのです。
誰も見ない場所で、完璧な演技指導が行われている。
この執念、狂気すら感じます。
スポンサーリンク
ナラティブの解剖崩壊した家庭と「204863」

ストーリーテリングも秀逸でした。
明確なナレーションやムービーはなく、ラジオのニュースや環境から物語を察するしかありません。
いわゆる「環境ストーリーテリング」の極致です。
ラジオが語るのは、ある父親による一家惨殺事件です。
「父親はライフルで妻を撃ち、その音に驚いて様子を見に来た10歳の息子も撃った。妊娠中の妻のお腹も」
「その後、ガレージでホースを使って首を吊った」
廊下に散乱する酒瓶、大量の抗うつ剤の錠剤。
これらは、父親が失業や経済的困窮、そして精神的な問題を抱えていた痕跡です。
シンクに置かれた異形の胎児(通称ベイビー)は、殺された未生まれの子の象徴であり、プレイヤーに向かって
「あんたがやったんだろ?」
と問いかけてきます。
つまり、プレイヤーはこの殺人鬼である父親の視点を追体験させられている(あるいは父親の煉獄を彷徨っている)という解釈が成り立ちます。
このドロドロとした家庭の崩壊劇。
ワイドショーで見るような現代社会の闇を、高解像度で突きつけられる不快感。
幽霊のリサは、単なるモンスターではなく、被害者なんですよね。
右目をえぐられ、笑っているようにも見える引きつった表情。
彼女が襲ってくるのは、理不尽な暴力への復讐なのかもしれません。
「204863」が示すもの
そして、執拗に繰り返される数字「204863」。
これには諸説あります。
最も有力なのは、小島秀夫監督の生年月日(1963年8月24日)のアナグラム説(20+4=24, 8月, 63年)です。
これが監督自身の署名であることはほぼ間違いないでしょう。
しかし、私が個人的に面白いと思ったのは「ポプラの木(Populus Trichocarpa)」の遺伝子モデル番号説です。
この木は、植物で初めて全ゲノムが解読された種。
「P.T.」は「Populus Trichocarpa」の略ではないか、と。
生命の樹、あるいはサイレントヒルの「森」への回帰。
まあ、深読みしすぎかもしれませんが、オタクというのはこういう考察を肴に酒を飲むのが好きな生き物なのです。
私も友人とこの話題だけでワイン2本空けたことがあります。
メタフィクションとしての「退職願」
ゲーム終盤、血まみれの紙袋が独り言を喋り出すシーンがあります。
「親父は退屈な奴だった(Dad was such a drag)」
「毎日同じ飯を食い、同じ服を着て、同じようなゲームの前に座って……でもある日、俺たちを皆殺しにしやがった! 殺り方すら独創性がなかったよ」
「俺は戻ってくるぜ。新しいオモチャを持ってな」
これ、誰のことだと思います?
多くのファンや評論家が、当時の「コナミ」と「小島監督」の関係性を暗喩していると指摘しました。
- 「親父」=保守的な経営陣
- 「皆殺し」=プロジェクトの中止やチームの解体
- 「新しいオモチャ」=Fox Engine、あるいは独立後の新たなテクノロジーやIP
もしそうだとしたら、これはゲームの中に隠された、世界で最も手の込んだ、そして最もロックな「退職願」であり「告発状」です。
会社員として、この姿勢には痺れますね。
私もいつか辞表を出すときは、プレゼン資料の中に謎の暗号を仕込んでやろうかしら。
なんて、小心者の私には無理ですけど。
スポンサーリンク
企業の論理による「デジタル焚書」事件

そして2015年、悪夢は現実となりました。
『SILENT HILLS』の開発中止。
そして『P.T.』の配信停止。
ここまでは、まあビジネスの世界ではあり得ることです。
しかしコナミは、さらに強硬な手段に出ました。
再ダウンロードすらブロックする
という、前代未聞の焦土作戦です。
通常、配信終了したゲームでも、一度ライブラリに追加していれば再ダウンロードできるのがデジタルの常識でした。
しかし、コナミはサーバーへのアクセスを完全に遮断しました。
一度手に入れたはずのデータが、企業の都合で奪われる。
これは「所有」という概念への挑戦であり、デジタルコンテンツの脆弱性を露呈させた事件でした。
その結果、何が起きたか。
『P.T.』が入ったままの中古のPS4が、eBayで1,000ドル(約15万円)、高いものではそれ以上の価格で取引される事態となりました。
行動経済学で言う
「希少性の原理」
が暴走したのです。
「もう手に入らない」
とわかった瞬間、人はそれに無限の価値を見出す。
さらに「心理的リアクタンス(抵抗)」も働きました。
「消された」ことへの反発心が、ファンの熱量を異常なまでに高めたのです。
15万円のPS4。
それはもはやゲーム機ではなく、現代のアートピース、あるいは「聖遺物」となってしまいました。
私の家にもPS4がありますが、残念ながら『P.T.』は入っていません。
もし入っていたら、息子の学費の足しに……
いやいや、そんな罰当たりなことはできませんね。
スポンサーリンク
継承される遺伝子P.T.ライクという亡霊たち

『P.T.』本体は殺されました。
しかし、その遺伝子は死ぬどころか、爆発的に増殖しました。
「P.T.ライク」というサブジャンルの誕生です。
『Visage』
『Layers of Fear』
『MADiSON』
一人称視点、閉鎖空間、ループ、戦闘なし。
これらの文法は、インディーホラーの標準規格となりました。
そして、あの大手カプコンすら動かしました。
2017年の『バイオハザード7 レジデント イービル』。
それまでのアクション路線を捨て、シリーズ初の全編一人称視点に回帰し、あの湿度の高い恐怖を描いた背景に、『P.T.』の影響がなかったとは言わせません。
実際、開発者も『P.T.』を見て「作り直したわけではないが、ライバルとして意識した」と語っています。
クリエイターたちは、「小島秀夫がやりたかったこと」を、それぞれの解釈で引き継ごうとしたのです。
ファンによる復元作業
ファンたちの執念も凄まじいものでした。
Qimsar氏やRadius Gordello氏によるリメイクプロジェクト。
Unreal Engineを使って、テクスチャ一枚、音の一つまで完全再現しようとする試み。
これらはコナミによって公開停止に追い込まれましたが、そのデータは今もネットの海を漂っています。
これはもはや「海賊版」というより、焼失した文化財を記憶だけで復元しようとする「宮大工」のような仕事です。
愛がなければ、あそこまでできません。
私も推しのアイドルのためなら何でもしますが、プログラムを一から組んでゲームを復元する情熱には脱帽です。
スポンサーリンク
結論我々の背後にいるもの
さて、配信停止から10年以上が経ちました。
小島監督は『Death Stranding』を経て、新作『OD』を発表しました。
トレイラー映像には、『P.T.』の匂いが色濃く残っています。
「親父」に壊されたオモチャの代わりに、もっと新しくて、もっと危険なオモチャを手に入れて、彼は帰ってきました。
『P.T.』とは何だったのか。
それは、ゲームという枠を超えた、巨大な
「認知バイアスの実験場」
であり、企業とクリエイターの軋轢が生んだ
「悲劇のアート」
でした。
私たちがL字型の廊下に囚われ続けているのは、リサの呪いではありません。
「失われた可能性」への執着という、私たち自身の心のバグなのです。
心理学に
「ツァイガルニク効果」
という言葉があります。
達成された課題より、中断された課題の方が強く記憶に残るという現象です。
もし『SILENT HILLS』が普通に発売されていたら?
きっと名作にはなったでしょうが、消費され、攻略され、やがて「過去のゲーム」になっていたはずです。
しかし、未完のまま殺されたことで、ファンの脳内で「理想の完全版」が永遠にアップデートされ続けているのです。
「逃がした魚は大きい」と言いますが、釣り上げる前に海が消滅してしまったようなものですから、その魚(作品)は神格化されるしかありません。
エピローグ
この記事を書きながら、ふと背後に気配を感じて振り返りました。
もちろん、誰もいません。
ただ、夫が飲み残したペットボトルがテーブルに置いてあるだけ。
でも、超論理的な視点で言えば、見えないからといって「いない」とは限らない。
リサは、あるいは『P.T.』という概念は、今も私たちの文化の背後に、ピッタリと張り付いているのかもしれません。
そう考えると、毎日の通勤電車も、終わらない家事ループも、少しだけドラマチックに見えてきませんか?
……いえ、やっぱり満員電車はただの地獄ですね。
おじさんの整髪料のにおいは、フォックスエンジンでも再現してほしくないものです。
さあ、そろそろ夕飯の支度をしないといけません。
今日の献立はハンバーグ。
冷蔵庫を開けたとき、中から赤ちゃんの泣き声がしないことを祈りつつ、現実という名のホラーゲームを攻略してきます。
以上、現場からお伝えしました。